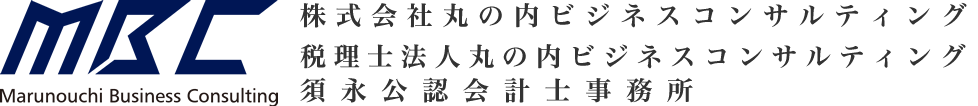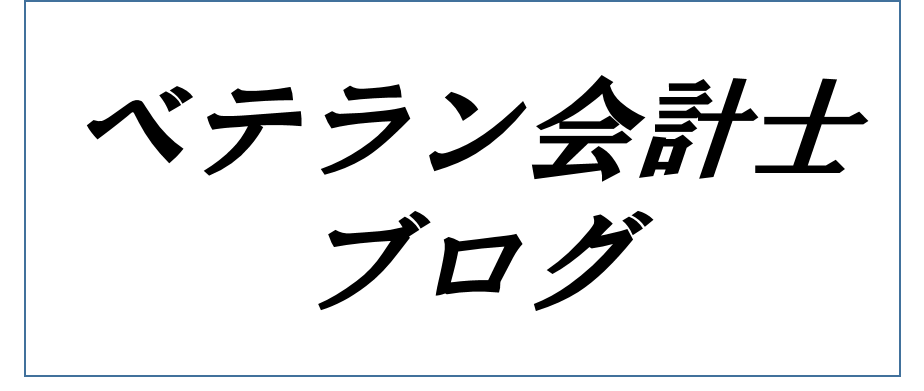でんた丸ブログ
前期損益修正の税務上の取扱い
前期損益修正自体は企業会計原則第二の六で認められています。そこで、前期損益修正益を会計上計上する場合に、税務上は、修正申告すべきでしょうか。また、前期損益修正損を会計上計上する場合に、税務上は、更正の請求をすべきでしょうか。この点については、当該前期損益修正という会計処理が税務上、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」(いわゆる「公正処理基準」、法人税法22条4項)に該当するか、と言い換えることができます。
ここでは、東京地判平成27年9月25日税資(税務訴訟資料)265号順号12725[過年度外注費当期損金算入事件]と東京地判平成25年10月30日判時2223号3頁[TFK事件](控訴審:東京高判平成26年4月23日訟月(訟務月報)60巻12号2655頁)という2つの裁判例を整合的に理解するために有効な次の基準を、私見ですがご紹介します。
すなわち、①当初の取引時に納税者が分かり得たにもかかわらず前期損益修正の会計処理をした場合には、公平な所得計算を実現し納税者の恣意を排除するという法人税法独自の観点からして、修正申告又は更正の請求をすべきとされます。
②一方で、納税者が当初の取引時には分かりえなかった収益や原価・費用・損失の存在が後になって判明したという場合には、益金又は損金の計上時期に関し納税者の恣意は問題とならないため、それが判明した事業年度の益金又は損金とするのが相当であり、過年度に遡って修正すべきではないとされます。
なお、法人税法上、修正申告や更正の制度(更正の請求の制度を含む。)があることに鑑みて、後に修正すべきことが発覚した場合には、過去の事業年度に遡って修正することが予定されており、原則は修正申告や更正の制度(更正の請求の制度を含む。)を利用することになります(更正の請求については、「更正の請求の原則的排他性」と呼ばれています)。
(参考)
・過年度外注費当期損金算入事件の事実の概要:納税者が過年度の外注費の計上漏れに気づき、当期に前期損益修正損を計上したところ、所轄税務署長から法人税・消費税の更正処分を受けた。
・TFK事件の事実の概要:会社更生法の適用を受けた貸金業を営む消費者金融会社が、過払金返還請求権が更生債権として確定したことを受けて、かつて受領した制限超過利息等に対して納付した過年度の法人税額について、後発的理由による更正の請求(国税通則法23条2項1号)をしたところ、所轄税務署長から、更正すべき理由がない旨の通知処分を受け、還付が認められなかった。
上記2つの事件において、各納税者は当該処分の適法性を裁判で争いましたが敗訴しました。
契約にリースが含まれているか否か(その6)
今回は、契約にリースが含まれているか否かを具体例を通して判定する最終回です。
前回に引き続き、適用指針第8項(1)又は(2)が満たされて、顧客が「資産の使用を指図する権利を有する場合(適用指針第5項(2)参照)に当たるか否かを検討します。
【具体例①:使用方法が契約で定められており、顧客が資産の使用を指図する権利を有していないケース】
1.顧客A社は、サプライヤーB社と、B社が所有する発電所が産出する電力のすべてを3年間にわたり購入する契約を締結した。
2.B社は、業界において認められた事業慣行に従い、日々当該発電所を稼働し、維持管理を行う。
3.契約において、使用期間全体を通じた当該発電所の使用方法(産出する電力の量及び時期)が定められており、契約上、緊急の状況などの特別な状況がなければ使用方法を変更することはできないことも定められている。
4.A社は当該発電所の設計に関与していない。
5.当該発電所は、特定された資産である。すなわち、適用指針第6項(1)又は(2)が満たされていない。
当該発電所の使用方法は契約で事前に定められているところ、A社は使用期間全体を通じて当該発電所を稼働する権利も有していないし(適用指針第8項(2)①参照)、当該発電所の設計もしていない(同項(2)②参照)。
よって、顧客は資産の使用を指図する権利を有しておらず、契約にリースが含まれていないと判断されます。
【具体例②:使用方法が契約で定められており、顧客が資産の使用を指図する権利を有しているケース】
具体例①の3.の部分を次のように変えると、適用指針第8項(1)を満たし、また他の要件も満たされているため、契約にリースが含まれていると判断されます。すなわち、
・顧客A社が当該発電所の使用方法(産出する電力の量及び時期)を決定する権利を有していることが契約で定められている。また、サプライヤーB社が他の契約を履行するために当該発電所を使用することができないことも契約で定められている。
【具体例③:使用方法が設計によって事前に決定されており、顧客が資産の使用を指図する権利を有しているケース】
1.顧客A社は、サプライヤーB社と、B社が新設する太陽光ファームが産出する電力のすべてを20年間にわたり購入する契約を締結した。
2.A社は、当該太陽光ファームを設計した。
3.B社は、A社の仕様に合わせて当該太陽光ファームを建設し、建設後に当該太陽光ファームの稼働及び維持管理を行う責任を有している。
4.当該太陽光ファームの使用方法(電力を産出するかどうか、いつ、どのくらい産出するか。)は、当該太陽光ファームの設計により決定されている。
5.当該太陽光ファームは、特定された資産である。すなわち、適用指針第6項(1)又は(2)が満たされていない。
上記2ないし4によれば、適用指針第8項(2)が満たされ、また他の要件も満たされているため、契約にリースが含まれていると判断されます。
契約にリースが含まれているか否か(その5)
会計基準第26項により、契約は、(1)資産が特定され、かつ、(2)特定された資産の使用を支配する権利を移転する場合に、リースを含むとされるところ、前回の(その4)までは、(1)の要件に関する具体例をみてきました。今回からは、(2)の要件に関する具体例をみていきます。
1.上記(2)の要件の内容
適用指針第5項により、顧客が、特定された資産の使用期間全体を通じて、①資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有し(同項(1)参照)、かつ、②資産の使用を指図する権利を有する場合(同項(2)参照)、資産の使用を支配する権利が移転することになります。
更に、適用指針第8項によれば、上記②について、(ア)使用期間全体を通じて使用から得られる経済的利益に影響を与える資産の使用方法を指図する権利を顧客が有しているか(同項(1)参照)、又は(イ)使用から得られる経済的利益に影響を与える資産の使用方法に係る決定が事前になされている場合に、(ⅰ)使用期間全体を通じて顧客のみが資産の稼働に関する権利を有しているとき、若しくは、(ⅱ)顧客が使用期間全体を通じた資産の使用方法を事前に決定するように資産の設計を行っているとき(同項(2)参照)に、顧客が資産の使用を指図する権利を有している、といえるとされます。
2.具体例
【顧客が資産の使用を指図する権利を有していない具体例】
・顧客A社は、2年間にわたりサプライヤーB社が提供するネットワーク・サービスを利用する契約を締結した。
・B社は、ネットワーク・サービスを提供するために、A社の敷地にサーバーを設置する。
・B社は、A社との契約で定められたネットワーク・サービスの水準を満たすようにデータの通信速度を決定し、必要に応じてサーバーの入替えを行うことができる。
・A社は、契約の締結時にネットワーク・サービスの水準を決定することができる。ただし、契約変更を行わない限り、使用期間全体を通じて、契約で定められたネットワーク・サービスの水準を変更することができない。
・A社は、サーバーを使用してどのようにデータを送信するのか、サーバーを再設定するのか、他の目的でサーバーを使用するのかどうかなどのサーバーの使用方法に関する重要な決定は行わない。
・A社は、設計に関与しておらず、サーバーを稼働する権利も有しない。
このような状況では、適用指針第8項の(1) (2)をともに満たさず、B社が当該サーバーの使用を指図する権利を有していることになります。A社は、契約で定められたネットワーク・サービスの水準の利用をすることができるのみで、契約にサーバーのリースは含まれていません。
【顧客が資産の使用を指図する権利を有している具体例】
・顧客A社は、サプライヤーB社と3年間にわたりサーバーを使用する契約を締結した。
・B社は、A社からの指示に基づき、A社の敷地にサーバーを設置し、使用期間全体を通じて、必要に応じてサーバーの修理及びメンテナンス・サービスを提供する。
・A社は、使用期間全体を通じて、A社の事業においてサーバーをどのように使用するのかや、当該サーバーにどのデータを保管するのかについての決定を行うことができる。
・当該サーバーは、特定された資産である。
このような状況に至ると、適用指針第8項(1)が満たされるため、A社は、使用期間全体を通じて、当該サーバーの使用を指図する権利を有しているといえます。そして、適用指針第5項の(1) (2)をともに満たし、さらに資産が特定されているため、契約には当該サーバーのリースが含まれることになります。
契約にリースが含まれているか否か(その4)
今回は、顧客A社が、ガスの貯蔵タンクを保有するサプライヤーB社との間で、B社が指定する貯蔵タンクにガスを貯蔵する契約を締結するケースを取り上げます。
1.具体例
以下の例で、資産は特定されているといえるでしょうか。
・貯蔵タンク内は物理的に区分されておらず、A社は、契約期間にわたりB社が指定する貯蔵タンクの容量の70%まで、ガスを貯蔵する権利を有している。
・貯蔵タンクの容量の残りの30%については、B社がガスを貯蔵することもできるし、他の顧客にガスを貯蔵する権利を与えることもできる。
2.規範
この例では会計基準第7項が規範となります。すなわち、「顧客が使用できる資産が物理的に別個のものではなく、資産の稼働能力の一部分である場合には、当該資産の稼働能力部分は特定された資産に該当しない。ただし、顧客が使用することができる資産が物理的に別個のものではないものの、顧客が使用することができる資産の稼働能力が、当該資産の稼働能力のほとんどすべてであることにより、顧客が当該資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有している場合は、当該資産の稼働能力部分は特定された資産に該当する。」
3.当てはめ
A社が使用できるB社が指定する貯蔵タンクの容量の70%は、物理的に別個のものではなく、また、貯蔵タンクの容量の70%は貯蔵タンクの容量全体のほとんどすべてに該当しません(99.9%なら、ほとんどすべてに該当します)。A社が使用することができる資産の稼働能力は、当該資産の稼働能力のほとんどすべてに該当しないため、A社は貯蔵タンクの使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有することとはなりません。
4.結論
契約においてA社が使用できる稼働能力部分は、特定された資産に該当せず、その結果、当該契約にはリースが含まれていないこととなります。
契約にリースが含まれているか否か(その3)
前回と同様に、サプライヤーが、①使用期間全体を通じて資産を他の資産に代替する実質上の能力を有し、かつ、②資産を代替する権利の行使により経済的利益を享受する場合には、当該資産は「特定された資産」に該当せず、当該契約にはリースが含まれないことになる、という規範(会計基準第6項)に関連する具体例をみてみます。
【「資産が特定されず、契約にリースが含まれていない」と判断される具体例】
1.顧客A社は、3年間にわたり、自社の商品を販売するために空港内の搭乗エリアにある区画を使用する契約を、空港運営会社であるサプライヤーB社と締結した。A社が使用できる面積及び割り当てられた区画は、契約で指定されている。
2.空港内には、利用可能で契約に定める区画の仕様を満たす多くの区画が存在する。B社は、A社に割り当てられた区画を使用期間中いつでも変更する権利を有しており、状況変化に対応するようにA社に割り当てた区画を変更することで、空港内の搭乗エリアにおける区画を最も有効に利用でき、経済的利益を得ることとなる。
3.A社は、商品を販売するために、容易に移動可能な売店(A社が所有)を使用することが求められている。A社に割り当てた区画の変更に関連するB社が負担するコストは限定的であるため、区画の変更によるB社の経済的利益はコストを上回ると見込まれる。
【「資産が特定される」と判断される具体例】
・上記2と3の太字部分を次のとおり変更すると、当該資産が「特定された資産」に該当するという結論に変わります。
すなわち、
2.B社は、A社の移転から生じるコストを全額負担する必要がある。
3.B社が当該移転コストを上回る経済的利益を享受することができるのは、B社が新たな大口テナントと小売エリア内の区画を使用する契約を締結したときのみであり、A社との契約時点において、このような状況が生じる可能性は高くないことが見込まれる。
上記の2つの例はともに、A社が外観上、契約で指定され割り当てられた区画で事業をしているという点において変わりがありません。しかしながら、B社が、冒頭に述べた「②資産を代替する権利の行使により経済的利益を享受する」といえるのかという経済的な判断により、当該資産が「特定された資産」に該当するか否かという結論が左右され、ひいてはリース会計基準が適用されるかどうかに影響することになります。