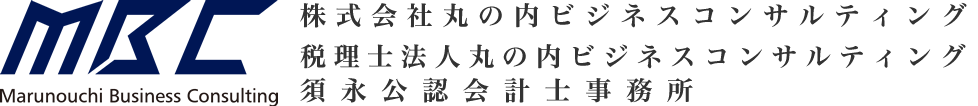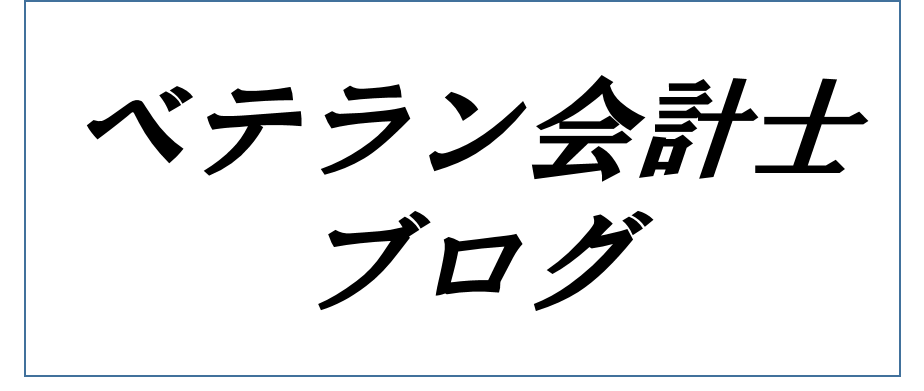でんた丸ブログ
申告納税制度と税理士制度
前々回と前回で、申告納税制度の水準を向上させるために青色申告制度が果たした役割について述べましたが、我が国において忘れてはならない制度として税理士制度があります。税務を専門とする職業が法律により制度化されている国は、日本以外にはドイツ、韓国、中国などしかなく、その他の多くの国では会計士や弁護士が税務サービスの提供を担っている状況にあります。
我が国では1947年に、所得税、法人税、相続税において申告納税制度が導入され、当該制度を支える職業的専門家として、従来の税務代理士(1932年に納税者からなされた請願を受け、1942年に税務代理士法が既に制定されていました。)が、新しく税理士(1951年に税理士法が制定されました。)へと生まれ変わりました。税理士法1条には、税理士の使命が次のように掲げられています。
税理士法1条
「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」
また、税理士法52条に、税理士業務(①税務代理、②税務書類の作成、③税務相談(同法2条))の無償独占が定められている点も特徴的です。
青色申告承認取消処分
様々な特典のある青色申告制度は、納税者が正しく記帳することによる納税者と課税庁との信頼関係が前提となっています。そして、その信頼関係を破壊するような、所得税法150条1項、法人税法127条1項に列挙された事由がある場合には、課税庁の裁量により青色申告の承認が遡及的に取り消されます。
遡及的に取り消された場合には、取り消された当該期間は白色申告となるため、当該期間内に享受した特典が遡って剥奪され、仮に課税庁に青色承認取消益が発生すれば、納税者はその分、過少申告になり白色申告に対する増額更正処分を受けることになります。更に納税者が逋脱罪で起訴されて有罪となった場合には、逋脱額に当該青色承認取消益が含まれることになります。
青色申告制度が適切に機能するよう、このような制裁が予め整備されています。
(注)青色申告承認取消処分については、除斥期間が設定されていませんので、青色申告承認の取消事由がある場合には、当該事由が生じてから大分、時間が経過した後に当該処分がなされる可能性があります。
青色申告制度
前回取り上げたシャウプ勧告において提案された諸制度のうち、特に重要とされるのが青色申告制度であり、昭和25年の税制改正で導入されました。昭和22年の税制改正により、これまで税額の確定において賦課課税方式が採用されていた所得税及び法人税で申告納税方式が導入され、昭和24年に国税庁が発足しましたが、その頃の日本の状況についてはシャウプ勧告の附録に次のような記述があります。
「今日(注:昭和24年当時)、日本における記帳は慨嘆すべき状態にある。多くの営利会社では帳簿記録を全然もたない。他の会社は有り余る程沢山もっていて、その納税者のみがどれが本当のものでどれが仮面にすぎないものかを知っている。」
営利会社ですらこのような惨状ですから、個人事業主にいたっては推して知るべしといえるでしょう。そこで、青色申告制度が導入され、青色申告をした場合には納税者に様々な特典を与えることで、帳簿に基づく正確・正直な申告を奨励しました。その結果、我が国の申告水準は大幅に向上しました。
ハロルド・モスとシャウプ勧告
ハロルド・モスについては、令和7年4月14日付け本ブログにおいて、昭和24年6月の国税庁の開庁式の祝辞で国税庁のスローガンとして「Respect among the honest; Fear among the dishonest(正直者には尊敬の的、悪徳者には畏怖の的)」と述べた人物として紹介いたしました。
ハロルド・モスは、当時、GHQ経済科学局内国歳入課長の職にあり、シャウプ使節団(ダグラス・マッカーサー占領軍総司令官がアメリカから招待した税制使節団)の編成と来日の準備・手配をしました。その後、昭和24年5月10日に来日したシャウプ使節団は、日本の税制と税務行政について同年8月26日まで日本に滞在して調査を行い、同年9月15日に「シャウプ使節団第一次日本税制報告書」いわゆるシャウプ勧告を公表しました。シャウプ勧告のシャウプというのは、シャウプ使節団の団長を務めたカール・シャウプという人の名前からとられており、当時46歳でコロンビア大学経済学部の教授の職にあった財政学者、租税理論家です。
シャウプ博士は、1972年に22年ぶりに再来日した際に行った講演の中で、当時実施した日本の税制と税務行政に関する調査について回顧し、次のように述べています。「地方旅行の際に、わたしどもはあちらこちらに長い車の列を止めまして、たとえば、日本の農村でお百姓さんが働いていると、そこで農民の方々にじかに日本の税をどう思うかとよく聞いたものです。私どもは、こういうことをしながら、いわば直接の、なまで、じかの国民の声を聞こうというふうに努めたわけであります。こういうことによって、日本の税制のかかえている問題点というものに対して、何らかの本質的な直感と申しますか、そういうものを得ることができたように思います。」(大蔵省広報誌『ファイナンス』1972年12月号)。
使用人賞与の損金算入時期
使用人賞与の損金算入時期は、法人税法22条3項1号の定める収益対応基準、又は同項2号の定める債務確定基準により判断されるところ、より具体的な基準が法人税法施行令72条の3に規定されています(法人税法65条に基づく委任立法)。この具体的な基準によれば、原則は使用人賞与の実際の支給日の属する事業年度が損金算入時期とされ、例外は以下の2つの場合しか認められていません。
① 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額の通知がされているもので、かつ、当該支給予定日又は当該通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理をしているものに限る。)
➡ 損金算入時期:当該支給予定日又は当該通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
② 次に掲げる要件の全てを満たす賞与 ➡ 損金算入時期:使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。
ロ イの通知をした金額を当該通知をした全ての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から一月以内に支払つていること。
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
(注)法人税基本通達9-2-43によれば、法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、法人税法施行令72条の3第2号イの支給額の通知には該当しない、とされています。
詳細は、国税庁HPタックスアンサーNo.5350をご覧ください。